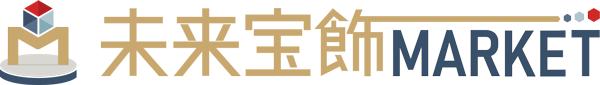ジルコン(Zircon)の知名度は高く、リングやネックレスなど多くの宝飾品に利用されています。ダイヤモンドに引けを取らない輝きを持つため、いわゆる「ダイヤモンド類似石」として注目を浴びてきましたが、今回の記事ではジルコンという宝石の特徴をより深くメス入れしていきたいと思います。
ジルコンは世界で一番古い?ジルコンの歴史
ジルコンは宝石の中で最も長い歴史を誇り、46億年以上も昔に誕生したと言われています。世の中に多く流通しているだけでなく、その多彩な色合いとダイヤモンドを思わせる強い輝きでジュエリーをより華やかに彩ります。
どんな宝石にも興味深い伝説がありますが、ジルコンは悪魔や妖怪を退け、狂気の苦しみから救い出す効果があると12世紀から伝えられています。またジルコンは人差し指に身に着けるべきというルールが過去にあったようですが、実際宝飾史の中ではこの決まりは重視されていなかったようです。
歴史が深い宝石だからこそ様々な伝承があり、それがジルコンという特徴深い宝石をよりミステリアスに、そして美しくしているのでしょう。
ジルコンの組成と特徴について

ここではジルコンの特徴について解説していきます。バキバキのファイヤーが美しいジルコンですが、実は鉱物として非常に珍しい特徴を兼ね備えた宝石なのです。
ジルコンの基礎データまとめ
まず簡単にジルコンの化学、物理的な特徴について見ていきましょう。
| 鉱物名 | ジルコン(Zircon) |
|---|---|
| 和名 | 風信子石(ヒヤシンスセキ)(※1) |
| 化学組成 | ZrSiO4 |
| 結晶系 | 正方晶系 |
| モース硬度 | 7.5(ハイタイプ)、 6.5(ロータイプ) |
| 劈開 | td テキストテキスト |
| 比重 | 4.67~4.73(ハイタイプ)、 3.95~4.10(ロータイプ) |
| 屈折率 | 1.925~1.984(ハイタイプ)、1.810~1.815(ロータイプ) |
| 複屈折率 | 0.059(ハイタイプ) |
(※1)ヒヤシンンスセキの風信子は花の名前ですが、宝石史の中ではサファイア、ガーネット、トパーズを含む様々な宝石を風信子と呼んでいたため、時代によって風信子が意味する宝石が違う場合があります。
ジルコンは無色(カラーレス)からレッド、オレンジ、イエロー、ブルーにグリーンなど様々な色合いがあり、その屈折率の高さがゆえの美しい煌きが特徴です。特に複屈折率が非常に高いため、ファセットの稜線部分(面と面が交わる角部分)が二重に見える「ダブリング」という現象が見られます。(ダブリング現象はジルコンと他の宝石を鑑別する際の重要なファクターになります)
上記の基礎データに「ハイタイプ」、「ロータイプ」とあり、ジルコンは大きく2種類に分かれます。ジルコンはウランなどの放射性元素を含んでおり、時間の経過とともに放射線の影響で結晶格子が破壊され、やがて非晶質になってしまいます。この現象を「メタミクト化」と呼んでいます。
ハイタイプのジルコンは完全な結晶を持ちますが、ロータイプのものは放射性物質により完全、部分的に非晶質化しており、それぞれ宝石としての特徴が異なります。なお、ハイタイプとロータイプの中間の性質を持つジルコンもあり、それを中間タイプまたはミディアムタイプと呼んでいます。ロータイプまたは中間タイプは主にグリーン系の色合いです。なおジルコンはメタミクト化の有無と程度により、光学的、物理的な特性、硬度がそれぞれ異なることも覚えておきましょう。
なお、ジルコンに含まれる放射性物質は非常に微量なものなので、人体に影響はありません。
ジルコンの欠点
ジルコンのモース硬度はジュエリー加工にも耐えうる十分な値ですが、宝飾品にセットされたジルコンは非常に角がダレやすい性質があります。
他の同硬度の宝石では見られないファセット部分の摩耗が非常に強いため、ルースを保管する際は他の石と混ざらないように注意する必要があります。また、リングにセットされたジルコンも上記の理由で目立つカケや摩耗が生じやすいので、ジュエリーに仕立てる場合はネックレスやピアスなどを推奨しています。
ジルコンの人為処理

ジルコンも他の宝石と同様に審美性を高めるための人為処理が行われています。天然ではブルージルコンの産出が非常に少ないため、通常加熱処理を加えてブルージルコンが得られます。ただし加熱の結果に形成された色合いが安定せず、温度や太陽光、放射線の影響で色が退色することも……。
また、ロータイプのジルコンは加熱を施すことでハイタイプに戻すことも可能です。以下がジルコンの主な人為的処理になります。
- ロータイプのジルコンを1400~1450度で加熱 →ハイタイプへ
- 褐色、赤褐色のジルコンを1000度で加熱 →ブルー、カラーレスジルコンへ
- ブルー、カラーレスジルコンに酸素を加え900度で加熱 →カラーレス、イエロー、レッドジルコンへ
合成ジルコンは存在する?
通常合成ジルコンが市場で見られることはありません。ただ商業ベースでは火炎溶融法、水熱法などで合成されており、研磨が十分できる大きさまで成長します。
現在合成ジルコンと呼ばれている合成宝石は天然ジルコンと同じ組成、特徴を持つ生粋の合成ジルコンではなく、合成スピネルまたはキュービックジルコニアを指す場合がほとんどです。
ジルコンが愛される理由とは?

ジルコンの宝石としての特徴について解説してみましたが、ここではジルコンが愛でられているその理由を考察していきたいと思います。
ジルコンが人気を博す3つの訳
ジルコンがキュービックジルコニアと同一視される傾向は日本だけでなく世界どこでも同様です。どちらも美しい宝石ですが、ジルコンが人気を博す理由はズバリダイヤモンドに似た性質があるからに尽きます。
ジルコンはダイヤモンドと異なる複屈折性の正方晶系で、特徴的なウランのスペクトルを示し、メタミクト化を起こすなど宝石としての特徴は全く異なりますが、パッと見ただけではダイヤモンドと見間違うような審美性を誇ります。
通常カラーレスジルコンがダイヤモンドの代わりとして長年利用され、その煌くブリリアンスと虹色のファイヤーは女性の心を奪ってきました。
またカラーバリエーションが豊富で加熱処理を施すと、驚くほどの透明度と彩度を見せるようになること。そして値段がダイヤモンドより圧倒的に安価なため、天然ダイヤモンドでは実現不可能なカラット&カラーのジルコンを手にすることができます。
前述の通り、ジルコンは非常に摩擦しやすいという弱点はありますが、そのデメリットを考慮に入れてもジルコンはルースマニア、宝飾品の知識がない一般層にも刺さる魅力がある宝石と言えるでしょう。
ティファニーのクンツ博士が情熱を傾けた宝石
ティファニー社専属で様々な宝石を入手し、クンツァイトの名づけ親としても知られるジョージ・フレデリック・クンツはお気に入りの宝石の1つとしてジルコンを挙げています。
関連記事:ティファニーのクンツ博士が惚れた宝石クンツァイトとは?その特徴を解説
ジルコンの幽玄で炎のような煌きに魅了された彼は、それを「スターライトストーン」と称えて、ジルコンを宣伝したほどです。実際ジルコンの別名候補スターライトストーンは定着しませんでしたが、稀代の宝石学者がジルコンに魅了された背景には、その歴史や目を見張る美しさ、そして宝石としての儚さ(脆さ)にあったのかもしれませんね。
なお、このスターライトという名称はブルージルコンに使われることもよくあります。ティファニーブルーは吸い込まれるようなブルージルコンの色にも似ていますが、現代のティファニージュエリーにジルコンは一般的ではありません。しかし、ルイス・コンフォート・ティファニー(※2)は非常に美しいブルージルコンとオレンジジルコンを使った幻想的なネックレスを制作し、圧倒的なスターライトストーンの美しさを芸術作品として表現しています。
(※2)ティファニーの創業者であるチャールズ・L・ティファニーの息子で、主にステンドグラスやランプなどのガラス工芸を制作。アメリカにおけるアール・ヌーヴォーを代表する作家であり、宝飾品制作も担った。
まとめ

ジルコンに関してまとめると、
- 世界最古の歴史を誇る宝石である
- 放射性元素による結晶構造の変化により、ハイタイプ、ロータイプに分かれる
- モース硬度が高い割に摩耗しやすい
- 豊富なカラーバリエーション、ダイヤモンドを思わせる輝きで人気
- ジョージ・クンツが恋をした宝石
ジルコンは天然の美しい宝石ですが、昨今はモアッサナイト、キュービックジルコニアなどより安価で強度のあるダイヤモンド類似石にその地位を脅かされ、また、ジルコン=模造石と勘違いされることも少なくありません。
宝飾品に一度セットされればその輝きと存在感に息を飲みますが、やはりファセット部分がダレてしまうことが多いため、その保管方法とケアには注意が必要です。
それでもジルコンが持つ悠久の歴史と性質は興味深く、カラットとカラー次第ではもっと評価されるべき宝石なのかもしれませんね。
関連記事
- ロシアはなぜ合成宝石産業が発展したのか?その背景を考察
- ダイヤモンドの人造・模造宝石一覧!その定義、特徴から見分け方まで
- ベリリウム拡散処理!消費者目線での定義と注意点【パパラチアサファイア】
- ティファニーのクンツ博士が惚れた宝石クンツァイトとは?その特徴を解説
- グランディディエライトの特徴と希少価値、今後の資産性を考察
- ジェダイスピネルとは?その特徴と産地、アジア圏で流行の理由を考察