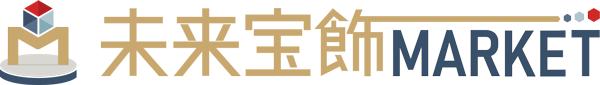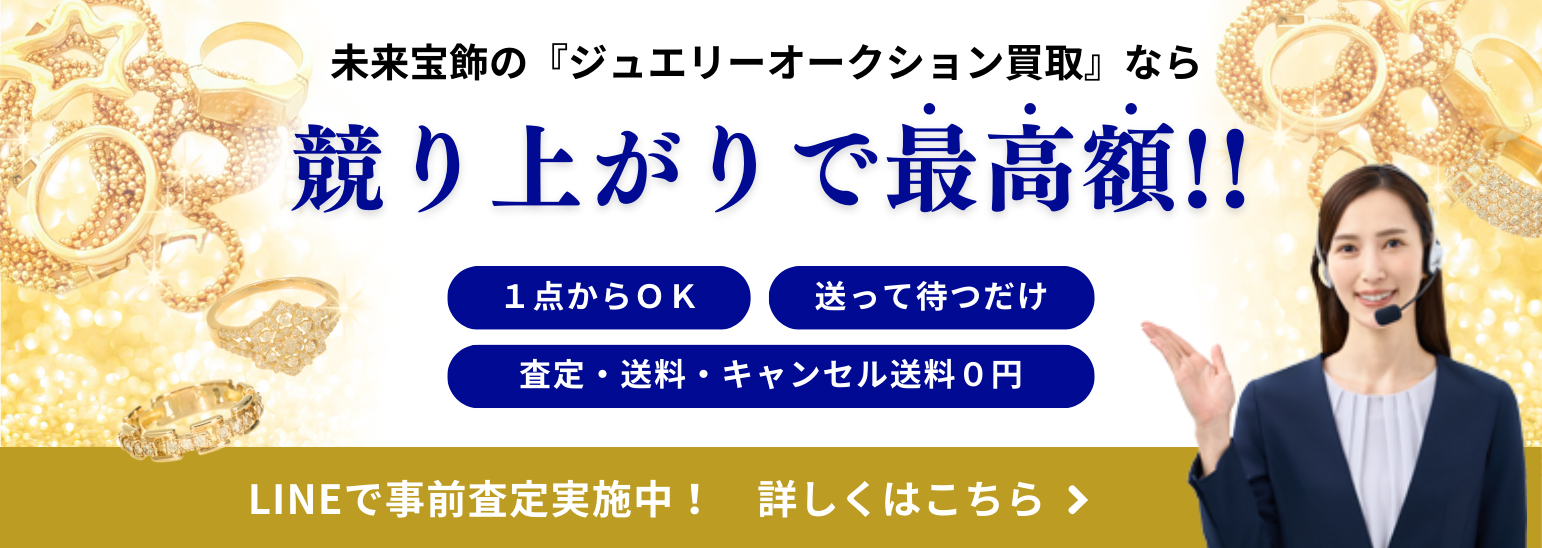宝石には歴史や文化に結びついたさまざまな逸話や由来が数多くありますが、今回はその中でも特に興味深く、あまり知られていないエピソードをご紹介します。宝石の輝きの裏に隠された意外なエピソードに触れ、その魅力を新たな視点からお楽しみください。
トルコ石はトルコでは採れない!?

世界で最古の宝石のひとつであるトルコ石ですが、最初に見つかったのは、現在のイラクにあたるメソポタミアや古代エジプトです。主な産地はイラン、中国、ペルシャ湾沿岸などで、トルコでは採掘されていません。それでは、なぜ「トルコ石」という名前が付いたのでしょうか?
かつて、トルコ石は地域によって異なる名前で呼ばれており、ギリシャでは「カライナ」、エジプトでは「メフカト」と呼ばれていました。しかし、ペルシャ産のこの鉱物がトルコを経由してフランスに運ばれた際に、「トルコの石」と呼ばれるようになり、その結果「トルコ石」という名前が定着したのです。
関連記事:鮮やかなブルーに酔いしれるターコイズ(トルコ石)とは
不可能だと笑われたアコヤ真珠の養殖

1800年代まで、天然の真珠は1万個の貝を開いてもほんの数個しか採れないほど希少なものでした。そのため、天然真珠を手にすることができるのは、ごく一部の限られた人々だけでした。そんな中、真珠の養殖に成功し、それを世界に広めたのが「ミキモト」の創始者、御木本幸吉です。「牡蠣が養殖できるなら、真珠貝も養殖できるはずだ」と考えた御木本は、1888年にアコヤ貝の養殖実験を始めましたが、当時は誰もが「成功するわけがない」と笑っていました。
実験開始から8年目の1905年、ついに真珠の養殖に成功しました。赤潮によって85万個の貝が死んでしまいましたが、その中の貝を開くと、大粒の丸い真珠が5個見つかったのです。これは、世界で初めて真円真珠の養殖に成功した瞬間でした。この成功を機に、真珠の養殖が本格的に始まり、真珠は一般庶民にも親しまれる宝石となったのです。
関連記事:養殖真珠の歴史を振り返る!人々が求めた叡智への旅【3】
サファイアは青しかなかった?誤解され続けた真実

1783年まで青以外のサファイアは「サファイア」ではなかった
サファイアには、ブルーサファイアをはじめ、ピンクサファイア、イエローサファイア、パパラチアサファイア、グリーンサファイアなどさまざまなカラーが存在しますが、1783年までサファイアといえばブルーしかありませんでした。
サファイアの種類が大幅に増えたのは18世紀のことです。それまで異なる鉱物とされていたサファイアとルビーが、1783年に同じ鉱物グループである「コランダム」だと判明しました。このとき、「ルビーは赤いコランダム、サファイアは赤以外のコランダム」と呼び分けられるようになり、サファイアは多彩な宝石として知られるようになったのです。現在では青はブルーサファイア、それ以外をファンシーカラーサファイアと呼びます。
関連記事:パパラチアサファイアの特徴と鑑別基準、人気の理由を解説
日本人が発見し、30年後に認められた新鉱物

発見者である日本人の名前が付いた「スギライト」という宝石があります。1944年、岩石学者の杉健一が愛媛県岩城島で小さな黄緑色の結晶を発見しました。しかし、当時は新鉱物だと認められず、数年後に杉氏は亡くなったのです。その後、杉健一の研究と分析を引き継いだ村上允英が、杉の名前にちなんで「スギライト」と命名。1976年に新鉱物として正式に認定された時には、杉健一の発見から30年以上が経過していました。
その後、南アフリカで発見された美しい紫色の鉱物もスギライトであることが判明し、アメリカで人気を博しました。しかし人々は、その名前が日本人に由来することに気づかなかったのです。これは、杉健一が発見したものと色が異なること、そして海外では「Sugilite」を「スジライト」と発音していたことが一因です。
アマゾナイトはアマゾン川とは無関係

アマゾン川で発見された鉱物は、実際はネフライトだった
アマゾナイトの名前はブラジルのアマゾン川に由来しますが、実際にはアマゾン川で採掘できません。アマゾナイトはフェルスパー(長石)グループに属する鉱物ですが、青緑色のフェルスパーは鉱山で採掘されるものであり、アマゾン川では採れないのです。
おそらく、アマゾン川で発見され「アマゾナイト」と名付けた別の鉱物と、名前がすり替わったまま商人が売り出したのでしょう。本来は白色である「微斜長石(びしゃちょうせき)」という鉱物の中で、青緑色のものがアマゾナイトです。アマゾナイトの和名は「天河石(てんがせき)」ですが、この「天河」はアマゾン川の当て字になっています。なお、アマゾン川で発見された鉱物はネフライトだったと言われています。
関連記事:憧れのティファニーブルーを身近に!よく似たカラーの宝石たち
宝石と蝶、異なる世界に共通する輝きの仕組み

左:ラブラドライト 右:モルフォ蝶
ラブラドライトという宝石は、光を当てると見る角度によってさまざまな色に輝きます。この効果を「イリデッセンス」といい、虹色に輝く美しいモルフォ蝶と同じ仕組みで光を反射しています。
和名を「曹灰長石(そうかいちょうせき)」と呼ぶラブラドライトは、内部に薄い曹長石(そうちょうせき)と灰長石(かいちょうせき)が重なり合っており、その層で反射した光が干渉し合うことで、虹のような輝きを生み出すのです。「世界で一番美しい蝶」と言われるモルフォ蝶も、羽の構造によって青く輝きます。ラブラドライトのこの独特な光の効果は「ラブラドレッセンス」と呼ばれています。
関連記事:レインボームーンストーンはなぜ七色に輝くのか?鉱物の秘密に迫る!
スペイン人は日本を「銀の島」と呼んでいた

世界の銀の約3分の1が採れていた島根県の石見銀山
日本のことを「黄金の国ジパング」と『東方見聞録』に記したのは、イタリアの商人マルコ・ポーロですが、スペイン人は日本を「銀の島」と呼んでいました。1549年に日本にキリスト教を伝えたスペイン人宣教師フランシスコ・ザビエルは、インドにいる父への手紙で「スペイン人は日本を『銀の島』と呼んでいる」と記しています。このころ、日本の銀の産出量は世界的に注目されており、その量は圧倒的で、世界の銀の約3分の1が島根県の石見(いわみ)銀山で採れていたのです。当時の戦国大名たち(豊臣秀吉など)は石見銀山を奪い合い、主要な収入源としていました。
1853年に開国を求めて来航したペリーの目的の一つも、日本の鉱物資源でした。現在、日本は自然資源が乏しい国というイメージがありますが、かつては金・銀・銅など、豊富な鉱物資源を誇っていたのです。石見銀山は1923年に採掘を終了し、2007年にはその遺跡が世界遺産に登録されました。
まとめ
- トルコでは採れないトルコ石の名前は「トルコを経由した石」に由来する
- 不可能と言われた真珠の養殖に成功したのは「ミキモト」の創始者、御木本幸吉
- 18世紀までサファイアは青しか存在しないと思われていた
- スギライトは日本人が発見し30年後に新鉱物と認められた
- アマゾナイトはアマゾン川で見つかった別の鉱物とすり替わったまま名前が付いた
- ラブラドライトとモルフォ蝶は同じ仕組みで輝く
- 鉱物資源豊富な日本をスペイン人は「銀の島」と呼んでいた
この記事を通して、宝石が単なる美の象徴だけでなく、時代や文化と深く結びついていることを感じていただけたのではないでしょうか。宝石の奥に秘められた物語に思いを馳せ、その魅力をより深く味わっていただければ幸いです。
大切なジュエリーを少しでも高く売りたい方へ
買取店を回らず高く売りたい方は、未来宝飾MARKETの「ジュエリーオークション買取」にお任せ下さい。お送りいただいた商品を、お客様に代わってオークションへ出品します。送った後はお家で落札結果を待つだけ!スピード重視の「宅配買取」もございます。
- オークション買取だから価格が競り上がる
- フリマアプリと違って「売れるタイミング」「価格交渉」のわずらわしさが無い
- プロのバイヤーが競るから相場が分からなくても安心◎
- 査定・返品送料・キャンセル料0円
関連記事
- 世界の博物館・美術館にある有名な宝石10選
- あなたはいくつ知っている?ダイヤモンドの雑学10選
- 価格が違うのはなぜ?似ている宝石の価値の違い
- ジュエリー・宝石のギネス世界記録6選!指輪にギターまで!
- 誕生石は意味がない!?誰が決たの?誕生石を持つ意味について
- ブルーガーネットの存在を検証!新発見の青いガーネットとは?