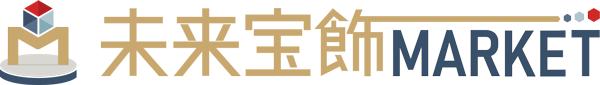サンストーンという宝石を聞いたことはあるでしょうか。スパンコールのようなオレンジやレッドの輝きを放つ宝石で、その名の通り太陽のような魅力のある宝石です。今回はサンストーンの基本知識と魅力をご案内します。
サンストーンとは
サンストーン(sunstone)は主に赤褐色をしており、石自体が光を放つような独特のキラキラした輝きが特徴の石です。赤色やオレンジ色のほか、黄色や褐色などをしています。
サンストーンの和名は「日長石(にっちょうせき)」といいます。まさに太陽を表していますね。実はこの名前、6月の誕生石であるムーンストーン(月長石)の対になるように付けられたそうですよ。
どちらも長石グループに所属する兄弟のような宝石になります。長石グループには他にもラブラドライトやオーソクレーズなどいろんな仲間がいます。
アメリカのオレゴン州で生活していた先住民族が1900年代の初期にサンストーンを見つけたという説があり、彼らにとって血のように見えるサンストーンはパワーの象徴だったそうですよ。1900年代初期といえば第一次世界大戦が終結したあたりですから、宝石の中では新参者になります。
鉱物としての特徴

サンストーンは鉱物の種類ではなく見た目から名前がつけられた宝石です。そのため同じサンストーンでも鉱物が違うことがあります。
どういうことかというと、例えば青い宝石の代表であるブルーサファイアの鉱物名はコランダムと言い、コランダム以外の鉱物がブルーサファイアと呼ばれることはありません。
一方サンストーンは、長石グループの鉱物の中で、アベンチュレッセンス(キラキラと輝く光学効果のこと)が見られる天然石全てをサンストーンと呼びます。この効果を持つことからサンストーンは、正式にはアベンチュリン・フェルドスパー(Aventurine feldspar)と呼ばれます。
鉱物はオリゴクレース、オーソクレーズ、アンデシン、アノーサイト、ラブラドライト、マイクロクラインなどがあり、どの鉱物からもサンストーンが見つかります。ちなみに一番サンストーンに多いのがオリゴクレースだそうですよ。
通常どの鉱物であっても「サンストーン」と表記する店が多い印象ですが、店によっては「オリゴクレース・サンストーン」や「ラブラドライト・サンストーン」と鉱物名を書いてくれているところもあります。
サンストーンの産出場所

サンストーンの主な産地はアメリカ、ノルウェー、インド、カナダ、ロシアです。非常に広い範囲から産出することがわかりますね。このようにサンストーンをはじめとした長石は世界中で取れますが、実際に美しい宝石質のものとなるとほとんどありません。
アメリカのオレゴン州から産出されるものはオレゴン・サンストーンと呼ばれ人気があります。
サンストーンの魅力の秘密
サンストーンがギラギラと輝く要因は、中に入っている内包物(インクルージョン)のおかげです。
ラメのようにも見える特徴的な輝きはアベンチュレッセンス(アベンチュリン効果)と呼ばれ、大小様々な平板状のインクルージョンが光に反射して起こる現象を言います。これには酸化鉄や銅が含まれていて、オレンジ〜赤色〜緑色を発色します。
インクルージョンの入り方によってサンストーンの見た目もかなり変わります。印象別にまとめてみました。
インクルージョンの多いサンストーン

透明な表面に大粒のインクルージョンがスパンコールのように輝くサンストーンは、夏の太陽を思わせるようなエネルギッシュさがあります。サンストーンと聞いてこのタイプを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。インクルージョンが密集しているとよりキラキラと華やかになりますよ。
インクルージョンの少ないサンストーン
サンストーンでも大粒のインクルージョンが少なく透明感のあるものはまた違った魅力があると思います。まばらに浮かんだ赤とオレンジの閃光が、澄んだ水の中を泳ぐ金魚を思わせます。目を惹きますが、どこか涼しげで落ち着いた雰囲気をしているのが魅力です。またグリーンや赤など地色によって印象が変わります。
透明感のあるもの

プリズムジュエルス オレゴンサンストーン ファンシーカット 7×15.5mm 2.13ct
オレゴンサンストーンの中にはアベンチュレッセンスを示さない透明感のあるものもあります。地色の美しさを楽しめるのが嬉しいですね。サンストーンの地色は赤〜オレンジが一般的ですが、黄色や無色透明のもの、グリーンのものなども存在します。
透明感のないもの

微細なインクルージョンが多かったりクラックが多いなど様々な要因で透明感がないサンストーンもあります。透明感のあるものと比べると優しくミルキーな雰囲気となります。地色が白っぽいと少しピンク系の色合いにみえることも。
サンストーンのアベンチュリン効果はみているだけで元気がもらえるような美しさがあります。個々の違いを楽しめる宝石ですから、手にいれる際は色んなサンストーンを見比べて選んでみてくださいね。
結びに
- サンストーンが見つかったのは1900年代と最近で、その見た目からムーンストーンの対になる宝石として名付けられた
- 「サンストーン」は見た目からつけられた名前であり、同じサンストーンでも個々で鉱物名が異なる
- 最大の魅力であるアベンチュリン効果は、入っている銅のインクルージョンの大きさ、量によって見え方が変わる
サンストーンが見つかったのは1900年代と最近で、その見た目からムーンストーンの対になる宝石として名付けられました。
サンストーンは鉱物の種類ではなく見た目から名前がつけられる宝石なので、同じサンストーンでも鉱物名が個々で違います。違う鉱物なのに同じ宝石名になるなんて不思議ですよね。それだけサンストーンの要素を持っている宝石は特徴的だったということなのでしょうか。
最大の魅力であるアベンチュリン効果は入っている銅のインクルージョンの大きさ、量によって見え方が変わります。あなたの好みにピッタリのサンストーンをぜひ探してみてください。
関連記事
- クォーツとは?宝石の種類と処理を解説<前編>
- ヒスイとは?二種類のヒスイの違いと人工処理の種類、分類を解説
- ジェットとは?格調ある漆黒の宝石の秘密とモードを考察!
- オパールの遊色模様の原理とパターンは?その種類と価値も検証!
- 養殖真珠の歴史を振り返る!御木本以前の養殖真珠の歴史【1】
- プリズマティンとは?玄人の心をくすぐるレアストーンの特徴とその魅力